皆さん、おはようございます。

こちらの記事で、ゲーム音楽と劇伴音楽の違いについて考えましたが、ゲーム音楽と劇伴音楽では楽曲自体の違いだけでなく、BGMの使い方も異なります。
BGMの使い方の違い
それは、「ゲームは四六時中BGMが流れ続ける」ということです。
もちろん、最近のゲームではその限りではありませんが、全体的にBGMは様々な種類使われているとは言え、無音状態になるというのは余程のことがない限り無いものです。
これについては、過去記事でも語っています。
掻い摘んで話すと、ゲーム中でBGMを無音にするというのは、あてがうBGMがないという意味でも静寂が欲しいという意味でもなく、無音を使うことが、これから起こることへの不安などを駆り立てる演出目的で使われることが多いためです。それは、ゲームをプレイしていて、無音になった時に不安や違和感を覚えることが物語っているでしょう。
それを除いても、なぜ何かしらのBGMを流し続ける必要があるのでしょうか。
正直、無音でも良い状況であっても、音量が小さくてもBGMが流れているということが大多数です。なぜ無音ではいけないのでしょうか…?
静寂でもBGMを流し続ける理由
ゲームのBGMが、視覚情報以上の情景をプレイヤーに提供するためです。
ゲーム画面からは、見える情報以上の情報は得られません。
また、街行く人の数も現実よりずっと少なく、ドラマのような喧騒に溢れた街をビジュアルで作り出すのはとても手間がかかります。
RPG作品を見ればわかりますが、すごく賑わっている街に主人公たちがいたとしても、実際街の人というオブジェクトの数は数えるほどしかありません。賑わっている街であるなら、数千人、数万人はいないとおかしいはずです。でもそれは不可能です…作る手間もそうですし、作ったら作ったで人がいっぱいで動きにくくなって苛立ちますし、ゲーム中の処理速度にも影響を与える…何より割りに合いません。
それでも、この街は大きい街だ、人が多くて賑わっているのがわかると感じられるのは、BGMがあるからです。
楽しくて軽快なBGMがあれば、人が集まって賑わっている感じ…
情熱的なリズムが聞こえれば、この街ではお祭をやっているのかな…
のんびりとしたメロディなら、人は少なく喧騒もない小さな村…
普段とBGMが違えば、イレギュラーな事態が起こったと察する…
BGMによって、視覚情報では供給できない情景に関する情報を補っています。
ドラマでBGMが少ない理由
ロケーションの際に喧騒も一緒に収録したり、演者が喋っているなど、BGMを流さなくても何かしらの音が聴こえている状態が多いので、BGMはどちらかというと、イベント・感情を表現するために使われることが多いです。
逆に、ドラマで常にBGMを流し続けていれば、視聴者が演者の声をしっかり聞き取れないことも懸念されます。ドラマのセリフは怒鳴り声みたいに大きなものから、かすれるような小さな声まで、その音量差は大きいもの。
ゲームのBGMがドラマ並みに少ない場合、無音の時間がとても長くなってしまいます。それでも最近のゲームであれば、フルボイスに近かったり、風や雨などの情景音を使ったり、歩けば常に足音がするなど、ドラマのワンシーンに近い場面を作り出すことはできるので、そういうゲームの場合は、BGMを当てはめなくてもさほど違和感がないかもしれません。
ただ、情景にリアリティを与えるような音を使えば、その分だけゲーム容量を圧迫するので、家庭用ゲームなどのハイエンドゲームならまだしも、アプリ容量とにらめっこすることが多い携帯端末でのアプリでは割に合わないのかもしれません。それなら素直にBGMだけ使ったほうが楽です。
携帯ゲームだと、どうしてもゲームをするタイミングやハードウェアの関係で、サウンド面は軽視されがちになる点は否めません。
しかし、ゲームでのBGMは、視覚情報という平面だけでなく、BGMにより奥行きを足すもの。プレイヤーをどんどん目の前の世界に引き込み、どんどん感情を揺さぶる…
BGMの制作により、ゲームをもっともっと、面白いものにするお手伝いができればと思います。
あなたのゲーム制作をお手伝い!
同人ゲームなどの個人制作から、コンシュマー、アプリ、PCゲームまでBGMの制作を承ります。お気軽にご相談ください。

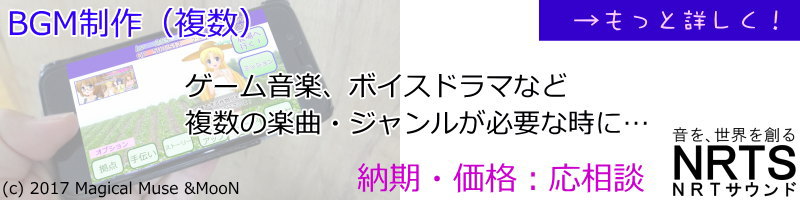
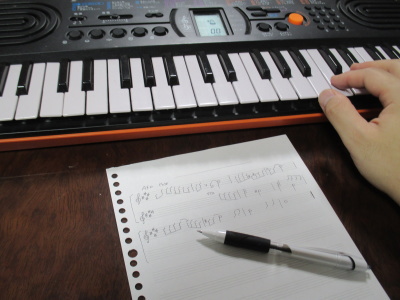



“なぜゲームはBGMを流しっ放しにするのか” への1件の返信