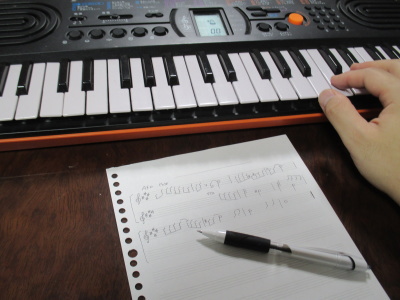皆さん、おはようございます。
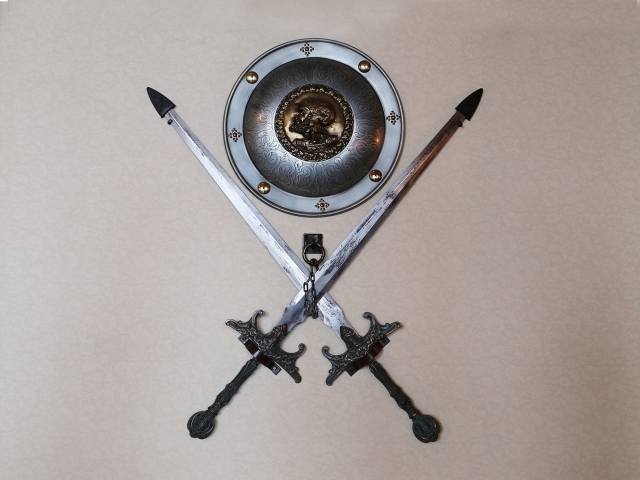
軍事と音、これらには密接な関係があります。
今回は軍事と音の関係が深いものを紹介したいと思います。
てつはう
元寇の時に使われた武器で、「鉄砲」ではなく、手りゅう弾のような武器で殺傷能力よりは炸裂して大きな音を出し、相手を威嚇する武器と言われている。
大きな音を出して威嚇することで、士気にもダメージを与える効果を持つ。
富士川の戦い
1180年、富士川で行われた源平合戦のひとつだが、平家軍は水鳥の群れが飛び立つ羽音に驚き、敵襲と勘違いして撤退した、戦力が正面からぶつかることのない戦のひとつ。
四面楚歌
中国の故事成語のひとつ。
周りに味方がいない、敵だらけの状況という意味で使われることが多い単語だが、漢軍と対立する楚の故郷の歌が、漢軍の四方から聞こえてきて、周りは敵だらけで孤立し、絶望してしまったことに由来する。
マーチ
行進曲としてひとつの音楽ジャンルを確立しているが、いわゆる軍隊が行進する際の音楽のこと。
スネアドラムの軽快なリズムを中心に、トランペットなどの金管楽器、フルートやクラリネットと言った木管楽器、タムタムや大太鼓といった打楽器で構成される。
日本では「軍艦マーチ」が有名。
このように、音、音楽は昔から軍事に密接に関わってきました。
当たり前ですが、音楽が戦争を煽り、戦争に用いられるような事態は金輪際起こってほしくはありません。
しかし、音というものが、たとえ生死をかけた環境においても、携わる人の心理に密接に関わってくるということを、今回の軍事と音の関係をもってお知らせするのがこの記事の目的です。
音には、音楽には、人の心を揺さぶる力があります。
音を作る者として、人の心に影響を与えるものを扱うことへの責任を今一度認知し、曲作りを進めたいものです。