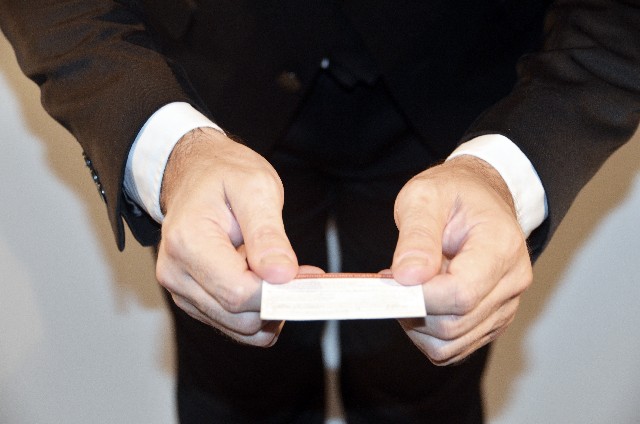皆さん、おはようございます。

連日報じられる様々なニュース。
その日にあった出来事やスポーツ速報、特集など様々ですが…中には目をそむけたくなる由々しい事件もある物です。
スポーツであれば、アップテンポなBGM、特集であれば季節感やイベント内容に合ったBGMが合いそうですね。
では、由々しいニュースに合うBGMは何でしょうか…?
それは…
無音
です。
BGMを用いない、と言う選択肢です。
例えば、凶悪事件が起こった際に、サスペンスドラマのような身の毛のよだつようなBGMをかけたらどうなるでしょうか…当たり前ですが不穏な空気になり、人によっては不快感や嫌悪感を覚えるでしょう。
そもそも、ニュースはその日に起こった出来事を伝えるのが目的であり、無用に不穏を煽ったりする必要はありません。ただ、ニュース番組も視聴率が気になる他の番組と同じ、どうしても番組としての面白さを追求しようと演出面に力を注いでしまうきらいは否めません。それに、凶悪事件などで使用したBGMをある時別の局面で耳にすれば、不快な記憶がフラッシュバックされるトリガーともなるでしょう。
ニュースはあくまでもニュースであり、何が起こったのかを的確に報じることが目的であるべきだと思います。そこにニュースを越えた手入れは必要ありません。特に直近では、ニュース番組に余計な脚色がされるがために視聴者から苦情が来るという事態もありますし。
楽曲を制作するだけが、サウンドクリエイター・サウンドデザイナーの仕事ではありません。場合によっては、BGMを使用しない勇気も必要となります。
音楽は人の感情に良い作用を与える反面、使い方を誤れば負の側面をもたらします。負の側面をもたらさないように注意をすることも、サウンド制作に携わる者の責務であると考えます。