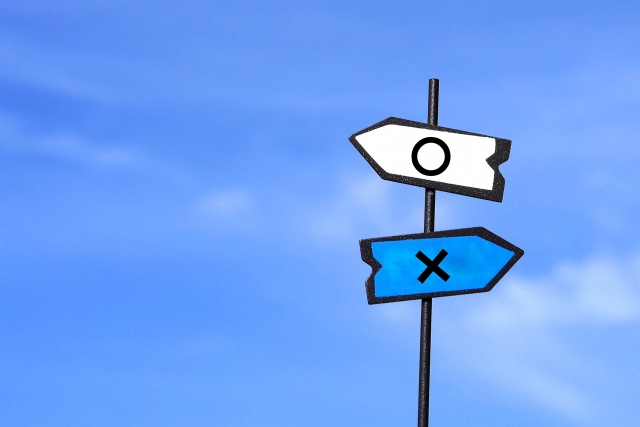皆さん、おはようございます。

2月と言えば確定申告ですね。
ちなみに確定申告は紙媒体で提出しています。それでも、金額の導出はExcelを使うなど、できるだけ手間を減らすようにはしています。
最近では経費申請や請求書の管理をスキャンしてAIがデータ化することを売りとしている経理ソフトや経理サービスが増えています。
ですが、AIでデータ化することについては、生成AIブームが来る前から導入しているケースもあり、すでにあるサービスでも、AIバブルの現在、AIを前面に出せば飛びつくことを狙っていると推測できます。
果たしてこのAIバブル、いつまで続くのでしょうか…
ただ正直、マイナンバーカードの制度が拡充して、キャッシュフローが明確化すれば、事業者や労働者を問わず、確定申告しなくても正しい税額を算出して自動的に納税(もしくは還付)することができるようになるとは思います。正しく納税されるだけでなく、社会情勢や年収を考慮し、臨時的な税金の還付についても適用が楽になるのではないでしょうか。
技術の進歩の背景にあるのは、効率化と時間の確保です。
どんなに技術が進歩しても、煩わしい事務作業があればそれに忙殺され、他の仕事に費やす時間や自分の余暇を潰すこととなってしまいます。そしてそれは、芸術職にとっては発信の機会を損ない、受信の機会を損ない、致命的となります。
技術の効率化は、時間や余暇を生むために使い、豊かな社会になることを願っています。